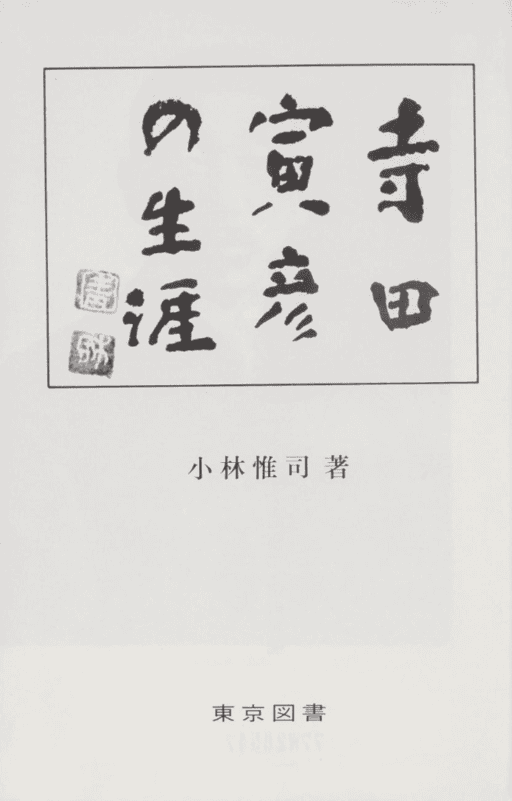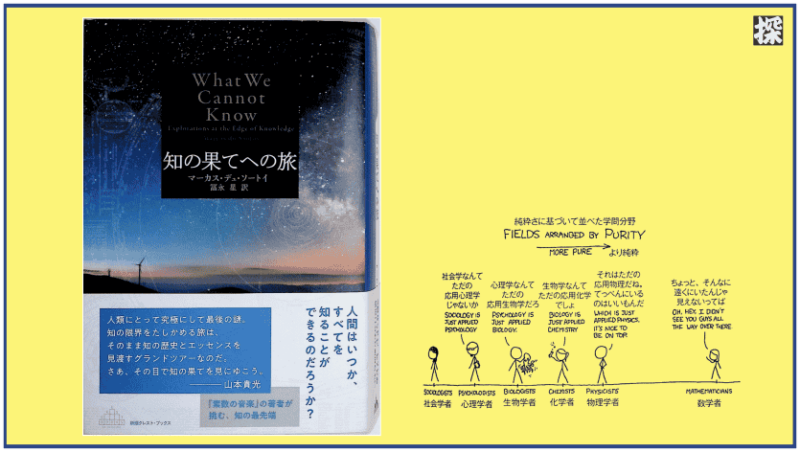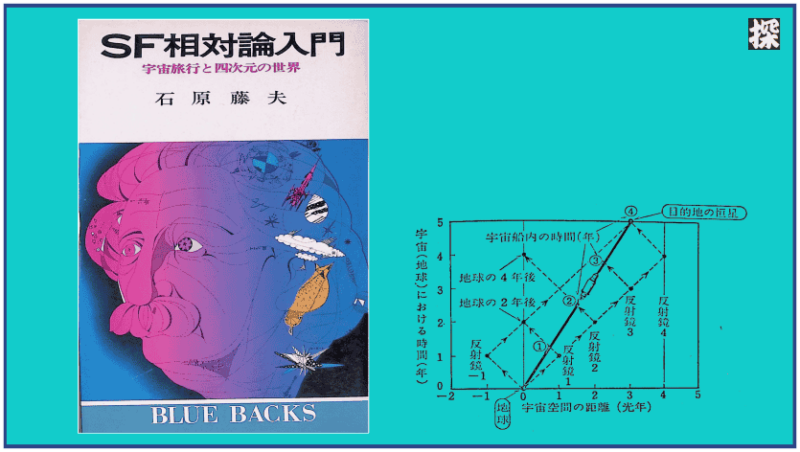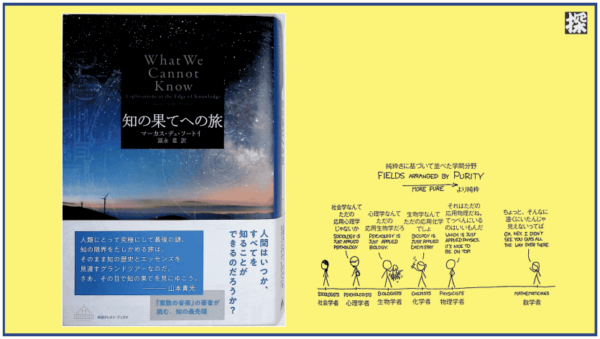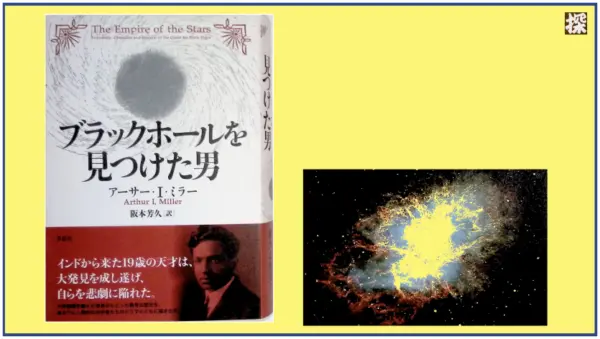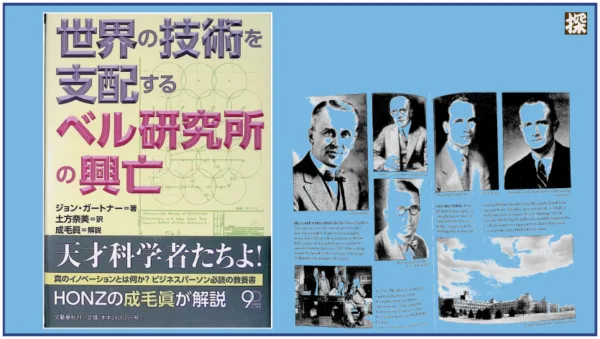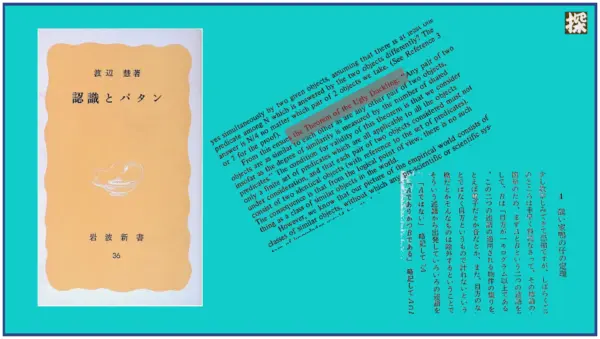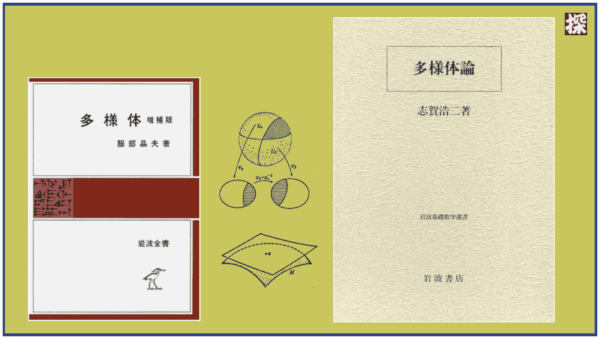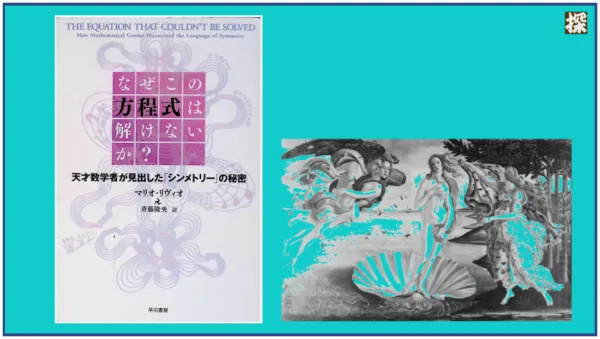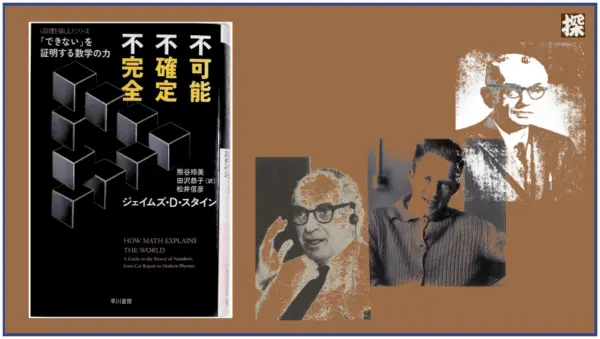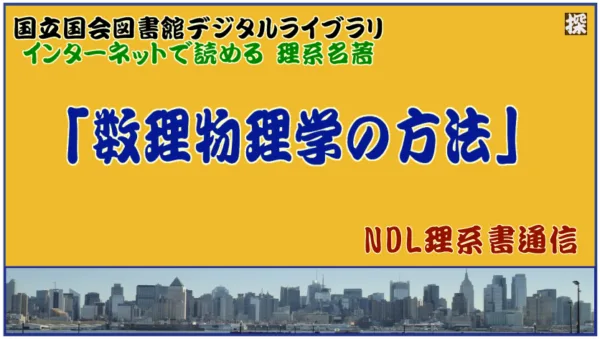◉ 文理融合の人、寺田寅彦。その科学者としての実像に迫るための第一級資料、『寺田寅彦全集 科學編』全6巻がインターネットで読める時代になりました。本稿では各巻をそれぞれ紹介します。第1巻から第5巻は欧文論文211編、最終巻には邦文論文58編がまとめられています。なお、ドイツ語論文はタイトルのみで本文は未収録です。
科学者としての寺田寅彦に迫るための第一級資料、『寺田寅彦全集 科學編』全6巻、欧文論文211編、邦文論文58編を収録。
この文章は、インターネットで読むことができる『寺田寅彦全集 科學編』全六巻の紹介記事です。寺田寅彦本人および『文學編』については、当サイトに関連記事があります。
≫当サイトの関連記事:『全集』探訪 No.1「寺田寅彦全集 文學編」へ
≫当サイトの関連記事:NDL理系書通信 第3報「寺田寅彦」へ
目次
1.はじめに
寺田寅彦(1878-1935)は夏目漱石の門下生で日本の物理学の黎明期に活躍した科学者。没後90年を迎えようとしていますが、寅彦の科学随筆は、万人の愛読書として世代を超えて読み継がれています。
この『寺田寅彦全集 科學編』では、理系から見た寺田寅彦、すなわち、寺田の物理学者、科学者としての真の姿に迫ることができます。寺田の名前を一挙に高めたのは、帝国学士院の恩賜賞受賞に輝くX線結晶解析の研究ですが、その後、主流から外れた物理学、いわゆる、主流派がいうところの「寺田物理学」に邁進します。線香花火、火花、キリンの斑模様、金属やガラスや地殻の破断面(割れ目)、金平糖の形状生成過程、墨流し等々、自己組織化、パターン形成、散逸構造論、生命物理に関連するテーマが目白押しです。弟子たちは、その独特の思考法と思いつきの新規さゆえに、寺田物理学を誇ります。私自身は、寺田本人より、むしろ寺田の生命観を継承した弟子、藤原咲平、平田森三、渡辺慧などに関心をもつ者ですが、寺田物理学の個々のテーマを深く追いかけている多くの人々がいます。例えば、金平糖は、あの「戸田格子」やソリトン研究で世界的に有名な戸田盛和(1917-2010)、別名 “おもちゃ博士” の餌食となってしまいました。しかし、ご安心を。まだまだ、美味しいテーマが『寺田寅彦全集 科學編』の中で、あなたを待っています。
2.『寺田寅彦全集 科學編』全6巻を眺める
このコーナーでは、国立国会図書館/デジタルコレクションの個人送信サービス(無料)を利用して、手元端末で閲覧可能な書籍を紹介します(PC・タブレット推奨)。記事のバナー【国立国会図書館デジタルコレクション】からログイン画面に入ります。未登録の場合、そこから「個人の登録利用者」の本登録(国内限定)に進むことができます。詳細は当webサイトの記事「国立国会図書館の個人向けデジタル化資料送信サービスについて」をご覧下さい。
2-1 『寺田寅彦全集 科學編 第一巻』
▼ 『Scientific Papers by Torahiko Terada VOL.1 1904-1909』、Iwanami Syoten(1939)、pp.372
この第一巻では、寺田寅彦全集刊行会による序文に続いて、19ページほどの簡単な英文の伝記があり、その後、寺田の論文が発表年順に収められています。
冒頭を飾る論文は1904年の「ジェット管によって生成される水銀のさざ波について」:
- On the Capillary Ripple on Mercury Produced by a Jet Tube、
capillary ripple(リップル)はさざ波(表面張力波あるいは表面張力重力波)。一般に、液体/気体間の界面に発生する波を考えて、その復元力として、表面張力が支配的である場合には表面張力波、重力も考慮する場合には表面張力重力波と言います。水銀の表面張力は常温で水の6.6倍、表面張力波の周波数は表面張力の平方根に比例しますから、水銀表面にジェット管で空気を吹きつけると、容器のヘリでの反射波との干渉も引き起こされて、何とも言えない美しい波紋が発生します。寅彦は、その美しさに魅せられ、うっとりするだけでは飽き足らず、それを「科学的に解明」したいと願ったわけです。25歳の学会デビュー。ところが、世界に認められる主流の論文を大量生産して研究業績を積み上げようという野心など、この論文には全く見られません。論文では、太口ノズルで一吹きすれば表面張力波、細口ノズルならば表面張力重力波であるとしたうえで、「この問題の完全な数学的な解明は我々の分析の範囲外」であるとしながらも、北斎漫画が線描で猫の跳躍の妙を完璧に捕らえるのに似て、簡単な数理解析からその本質に迫ります。これを称して、「寺田は物理現象の定性的な説明に終始するだけの実験物理屋だ」などという研究者もいますが、この問題、あのリチャード・ファインマンですら、自身の有名な教科書の中で「最悪の例」とか、「なかなか面白いがまた複雑」などと言っています。そのくせ、寺田と同様、学生、そっちのけで、その模様の複雑さを自分だけで楽しんでいるので、読者もついつい引き込まれてしまいます(『ファインマン物理学 Ⅱ 光 熱 波動』の26-4 表面波)。21世紀の現代ならば、計算物理学の格好の題材ですね。
この第一巻では、学位論文「尺八の音響学的研究」に関連した論文が目を引きますね。海洋潮汐、熱海の間欠泉、強磁性体、ドラムの振動、伊豆大島の火山など、地球物理学関連の論文が大半を占めます。寺田寅彦の存命中においても、「寺田の物理は古くさい」と陰口をたたく研究者が多かったと伝えられていますが、複雑すぎて数理的な解析では手も足も出ないような現象を、研究上、何の積み上げもない「原点」から見つめ、その本質を俳諧のごとく把握するのが寺田物理学。研究の積み上げも新陳代謝もありませんから、古びようがありません。常に「はじめの一歩」なのです。そして、100年以上を経過してもなお、未解決な問題が多いのも当然かと思います。
- On the Capillary Ripple on Mercury Produced by a Jet Tube (Proc. Tokyo Phys.-Math. Soc., II, pp.133-139, 1904)
- On the Geyser in Atami (Proc. Tokyo Phys.-Math. Soc., II, pp.164-172, 1904)
- A Note on Resonance-Box (Proc.Tokyo Phys.-Math. Soc., II, pp.211-216, 1904)
- On the Secondary Undulations of Oceanic Tide (Proc. Tokyo Phys.-Math. Soc., II, pp.222-232, 1904)
- A Tide Rectifier, or an Instrument for Eliminating the Tidal Components from Tide-Gauge Diagrams (Publ. Earthq. Inv. Com., XVIII, pp.117-120, 1904)
- LISSAJOUS'S Figures by Tank Oscillation (Nature, LXXI, p.296, 1905)
- Uber die sekundaren Wellenbewegungen der Meeresgezeiten (Phys. Zeits., VI, pp.115-119, 1905)
- Acoustical Notes (Proc. Tokyo Phys.-Math. Soc., II, pp.312-315, 1905)
- Acoustical Notes (Proc. Tokyo Phys.-Math. Soc., II, pp.332-334, 1905)
- On the Change of Elastic Constants of Ferromagnetic Substances by Magnetization (Proc. Tokyo Phys.-Math. Soc., II, pp.381-390, 1905)
- On the Whistle Produced by the Vibration of a Liquid Drop; and Its Application (Proc. Tokyo Phys.-Math. Soc., II, pp.407-412, 1905)
- Uber die Veranderung der Elastizitatskonstanten durch Magnetisierung (Phys. Zeits., VI, pp.622-628, 1905)
- A Polarisation Pattern (Nature, LXXII, p.581, 1905)
- On the Change of the Geyser of Atami (Proc. Tokyo Phys.-Math. Soc., II, pp.433-442, 1905)
- An Acoustical Method for the Demonstration of the Magnetism of Liquids (Nature, LXXIII, p.197, 1905)
- On the Geyser in Atami (Publ. Earthq. Inv. Com., XXII B, pp.51-73, 1906)
- Effects of Stress on Magnetization and Its Reciprocal Relations to the Change of Elastic Constants by Magnetization (Proc. Tokyo Math.-Phys. Soc., III, pp.27-39, 1906)
- On Syakuhati (Proc. Tokyo Math.-Phys. Soc., III, pp.83-87, 1906)
- On the Geyser in Atami, Japan (Phys. Rev., XXII, pp.300-311, 1906)
- On the Vibration of a Bar Floating on a Liquid Surface (Proc. Tokyo Math.-Phys. Soc., III, pp.103-109, 1906)
- Die Wirkungen der Spannung auf die Magnetisierung und ihre wechselseitigen Beziehungen zur Anderung der elastischen Konstanten durch die Magnetisierung (Phys. Zeits., VII, pp.465-471, 1906)
- Die Schwingung des Resonanzkastens (Phys. Zeits., VII, pp.602-604, 1906)
- Optical Illusions on Electric Fan (Nature, LXXIV, p.540, 1906)
- Uber den durch die Schwingungen eines Flussigkeitstropfens hervorgebrachten Pfeifton und seine Anwendung (Phys. Zeits., VII, pp.714-716, 1906)
- On the Change of Elastic Constants of Ferromagnetic Substances by Magnetization (Journ. Coll. Sc., XXI, Art.4, pp.1-70, 1906)
- Notes on Seiches (Proc. Tokyo Math.-Phys. Soc., III, pp.174-181, 1906)
- Uber die Schwinungen eines Stabes,dre auf einer Flussigkeitsoberflache schwimmt (Phys. Zeits., VII, pp.852-855, 1906)
- On the Effect of Stress on Magnetization and Its Reciprocal Relations to the Change of Elastic Constants by Magnetization (Journ. Coll. Sc., XXI, Art.7, pp.1-66, 1906)
- On the Change of Elastic Constants of Ferromagnetic Substances by Magnetization (Phil. Mag., XIII, pp.36-83, 1907)
- Perception of Relief by Monocular Vision (Nature, LXXV, p.224, 1907)
- Acoustical Investigation of the Japanese Bamboo Pipe,Syakuhati (Journ. Coll. Sc., XXI, Art.10, pp.1-34, 1907)
- On the Secondary Undulations of Oceanic Tides (Proc. Tokyo Math.-Phys. Soc., IV, pp.79-88, 1907)
- On Transverse Vibrations of Wooden Plates (Proc.Tokyo Math.-Phys. Soc., IV, pp.122-125, 1907)
- On the Effect of Stree on Magnetization and Its Reciprocal Relations to the Change of Elastic Constants by Magnetization (Phil. Mag., XIV, pp.65-115, 1907)
- On the Secondary Undulations of Oceanic Tides (Phil. Mag., XV, pp.88-126, 1908)
- An Investigation on the Secondary Undulations of Oceanic Tides (Journ. Coll. Sc., XXIV, pp.1-110, 1908)
- On the Secondary Undulations of Oceanic Tides (Publ. Earthq. Inv. Com., XXVI B, pp.1-113, 1908)
- Note on a Method of Constructing Contour Lines of Oscillating Liquid Surface (Proc. Tokyo Math.-Phys. Soc., IV, pp.251-255, 1908)
- The Volcano of Oshima,Its Past and Present (Proc. Tokyo Math.-Phys. Soc., IV, pp.293-312, 1908)
- Note on Vibrations of Drum (Proc.Tokyo Math.-Phys. Soc., IV, pp.345-350, 1908)
- Some Photographs of Projectiles in Flight (Proc. Tokyo Math.-Phys. Soc., IV, pp.398-404, 1908)
- On the Motion of Projectile after Penetration (Proc. Tokyo Math.-Phys. Soc., IV, pp.404-414, 1908)
- On the Relation between Seismic Frequency and Isobar Gradient (Proc. Tokyo Math.-Phys. Soc., IV, pp.454-459, 1908)
2-2 『寺田寅彦全集 科學編 第二巻』
▼ 『Scientific Papers by Torahiko Terada VOL.2 1910-1925』、Iwanami Syoten(1938)、pp.370
この第二巻には、X線結晶解析関連の論文が収められています。大半が、地磁気、降雨と降水量、日本沿岸での風や突風、地震、太陽黒点など、地球物理、天文、気象関連の論文です。光泳動などもありますね。
- Reply to Prof. AICHI'S Remark (Proc. Tokyo Math.-Phys. Soc., v, pp.301-302, 1910)
- Secondary Undulations of Tides Caused by Cyclonic Storms (Proc. Tokyo Math.-Phys. Soc., VI, pp.196-201, 1912)
- On the Velocity of Sea-Waves (Proc. Tokyo Math.-Phys. Soc., VI, pp.260-265, 1912)
- X-Rays and Crystals (Nature, XCI, pp.135-136, 1913)
- X-Rays and Crystals (Nature, XCI, p.213, 1913)
- On the Transmission of X-Rays through Crystals (Proc. Tokyo Math.-Phys. Soc., VII, pp.60-70, 1913)
- On a Typical Form of Isobars (Proc. Tokyo Math.-Phys. Soc., VII, pp.258-264, 1914)
- Deformation of Rock Salt Crystal (Proc. Tokyo Math.-Phys. Soc., VII, pp.290-291, 1914)
- On the Molecular Structure of Common Alum (Proc.Tokyo Math.-Phys. Soc., VII, pp.292-296, 1914)
- On the Noise of Breaking Sea-Waves and Some Optical Analogies (Proc. Tokyo Math.-Phys. Soc., VIII, pp.164-173, 1915)
- On the Distribution of the Cyclonic Precipitations (Proc. Tokyo Math.-Phys. Soc., VIII, pp.382-384, 1915)
- On the Distribution of Cyclonic Precipitation in Japan (Journ. Coll. Sc., XXXVII, Art.4, pp.1-32, 1916)
- Apparent Periodicities of Accidental Phenomena (Proc.Tokyo Math.-Phys.Soc., VIII, pp.492-496, 1916)
- On the Pulsatory Variations of Terrestrial Magnetism (Proc.Tokyo Math.-Phys.Soc., VIII, pp.566-570, 1916)
- On Rapid Periodic Variations of Terrestrial Magnetism.Part I and II (Journ. Coll. Sc., XXXVII, Art.9, pp.1-23, 1917)
- On Rapid Periodic Variations of Terrestrial Magnetism.Part III (Journ. Coll. Sc., XXXVII, Art.9, pp.23-47, 1917)
- On Rapid Periodic Variations of Terrestrial Magnetism.Part IV (Journ. Coll. Sc., XXXVII, Art.9, pp.47-85, 1917)
- On Irregular Assemblage of Pulses and Its Action on Resonators.I (Proc.Tokyo Math.-Phys.Soc., IX, pp.142-154, 1917)
- On Diurnal Variation of Barometric Pressure (Journ. Coll. Sc., XLI, Art.1, pp.1-30, 1917)
- Geophysical Notes.I.On the Temperature Distribution of a Pond (Proc.Tokyo Math.-Phys.Soc., IX, pp.240-243, 1917)
- On the Frequency of Earthquake and Allied Phenomena (Proc.Tokyo Math.-Phys.Soc., IX, pp.515-522, 1918)
- On the Analogy of the Temperature Variation of Nova Aquilae and the Frequency Variation of the After-Shocks of Earthquakes (Proc.Phys.-Math.Soc., I, pp.180-185, 1919)
- On a Model of Radioactive Atoms (Proc.Phys.-Math.Soc., I, pp.185-195, 1919)
- Barometric Gradient and Earthquake Frequency (Proc.Phys.-Math.Soc., I, pp.343-347, 1919)
- On the Effect of Topography on the Precipitation in Japan (Journ. Coll. Sc., XLI, Art.5, pp.1-24, 1919)
- On the Sound of Aeroplane and the Structure of Wind (Proc.Phys.-Math.Soc., IV, pp.43-46, 1922)
- On Photophoresis (Proc.Phys.-Math.Soc., IV, pp.67-70, 1922)
- On Resultants of Wind (Proc.Phys.-Math.Soc., IV, pp.125-133, 1922)
- Solar Activity and Atmospheric Pressure (Jap. Journ. Astron. Geophys., I, pp.27-42, 1922)
- Solar Faculae and Track of Cyclone (Jap. Journ. Astron. Geophys., I, pp.43-45, 1922)
- Influence of Wind, Air Temperature and Solar Radiation upon Sea-Water Temperature (Jap. Journ. Astron. Geophys., I, pp.47-49, 1922)
- On the Diurnal Variation of Winds in Different Coastal Stations of Japan (Rep. Aeron. Res. Inst., I, pp.35-85, 1922)
- On Periodic Fluctuations of Convection Current-With a Hint on the Origin of Sun-Spots Cycle (Proc.Phys.-Math.Soc., IV, pp.162-169, 1922)
- On Some Remarkable Relations between the Yearly Variations of Terrestrial Phenomena and Solar Activities (Journ. Coll. Sc., XLIV, Art.6, pp.1-20, 1923)
- Effect of Topography on Gustiness of Winds (Jap. Journ. Astron. Geophys., III, pp.1-6, 1925)
- Solar Activity and Atmospheric Pressure (Nagaoka Anniversary Volume, pp.137-152, 1925)
2-3 『寺田寅彦全集 科學編 第三巻』
▼ 『Scientific Papers by Torahiko Terada VOL. 3 1926-1928』、Iwanami Syoten(1937)、pp.519
この第三巻には、1923年9月1日の関東大震災の研究成果が収録されています。雷の放電現象、火花、電熱現象、地震によって生じた地殻変動、地震波、回転円筒間の流れの安定性や海洋物理、気象学関係の論文があります。
- Mechanism of Lightning Discharge (Proc.Imp.Acad., II, pp.15-16, 1926)
- Some Experiments on Spark Discharge in Heterogeneous Media-A Hint on the Mechanism of Lightning Discharge (Scient. Pap. Inst. Phys. Chem.Res., IV, pp.129-160, 1926)
- A Historical Sketch of the Development of Seismology in Japan (Scientific Japan, pp.251-310, 1926)
- Some Experiments on Motion of Fluids.PartI, II, III (Rep. Aeron. Res. Inst., II, pp.87-112, 1926)
- On the Effects of Winds on Sea-Level (Jap. Journ. Astron. Geophys., IV, pp.1-20, 1926)
- A Preliminary Note on the Form and Structure of Long Spark (Proc.Imp.Acad., II, pp.258-260, 1926)
- Propagation of Combustion in Gaseous Mixture (Proc.Imp.Acad., II, pp.261-263, 1926)
- On Thermoelectric and Electrothermal Properties of Bismuth Single Crystal (Proc.Imp.Acad., III, pp.132-135, 1927)
- Experimental Study on the Combustion of Mixtures of Hydrogen with Air or Oxygen in Eudiometer (Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res., VI, pp.81-127, 1927)
- On Thermoelectric Phenomena of Thin Metallic Films (Proc.Imp.Acad., III, pp.1-4, 1927)
- On a Long Period Fluctuation in Latitude of the Macroseismic Zone of the Earth (Proc.Imp.Acad., III, pp.275-278, 1927)
- On the Vortical Motion of Fluid Produced by Rotating Body (Proc.Imp.Acad., III, pp.419-421, 1927)
- Some Experiments on Motion of Fluids.Part IV (Rep. Aeron. Res. Inst., II, pp.287-326, 1927)
- Introduction to the Paper“Experimental Studies on Elastic Waves”by Ch.TSUBOI (Bull. Earthq. Res. Inst., III, pp.55-57, 1927)
- On a Zone of Islands Fringing the Japan Sea Coast-With a Discussion on Its Possible Origin (Bull. Earthq. Res. Inst., III, pp.67-85, 1927)
- Formation of Periodic Columnar Vortices by Convection (Proc.Imp.Acad., III, pp.503-506, 1927)
- Residual Thermoelectric Phenomena of Apparently Homogeneous Wire (Proc.Imp.Acad., III, pp.507-509, 1927)
- Residual Thermoelectric Phenomena of Apparently Homogeneous Wire (Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res., VII, pp.201-235, 1927)
- On the Mechanism of Formation of Step-Faults in Sand Layers-A Possible Analogy with Slip Bands in Deformed Metallic Crystals (Proc.Imp.Acad., III, pp.655-658, 1927)
- Experimental Studies on Form and Structure of Sparks.Part I (Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res., VIII, pp.1-19, 1928)
- Some Experiments on Periodic Columnar Forms of Vortices Caused by Convection (Rep. Aeron. Res. Inst., III, pp.3-47, 1928)
- Experimental Studies on Form and Structure of Sparks.Part II (Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res., VIII, pp.63-82, 1928)
- On the Vertical Displacement of the Sea Bottom in Sagami Bay Discovered after the Great Kwanto Earthquake of 1923 (Proc.Imp.Acad., IV, pp.45-48, 1928)
- On the Horizontal Displacements of the Primary Trigonometrical Points Discovered after the Kwanto Earthquake (Proc.Imp.Acad., IV, pp.49-52, 1928)
- On the Geophysical Significance of the Crustal Movement Found after the Great Earthquake of 1923 (Proc.Imp.Acad., IV, pp.53-55, 1928)
- Experiments on the Modes of Deformation of a Layer of Granular Mass Floating on Liquid-Some Application to Geophysical Phenomena (Bull. Earthq. Res. Inst., IV, pp.21-32, 1928)
- Experimental Investigations on the Mechanism of Formation of Step-Faults in a Pile of Sand (Bull. Earthq. Res. Inst., IV, pp.33-35, 1928)
- On the Relief of the Earth Crust on the Southern Coast of the Province of Tosa, Sikoku (Bull. Earthq. Res. Inst., IV, p.67, 1928)
- On an Irregular Mode of Spherical Propagation of Flame (Proc.Imp.Acad., IV, pp.98-101, 1928)
- Experimental Studies on Form and Structure of Sparks.Part III (Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res., VIII, pp.103-129, 1928)
- On Gustiness of Winds (Proc.Imp.Acad., IV, pp.145-147, 1928)
- Effect of an Irregular Succession of Impulses upon a Simple Vibrating System-Its Bearing upon Seismometry (Proc.Imp.Acad., IV, pp.208-210, 1928)
- On the Horizontal Displacements of Earth Crust Produced by Tango Earthquake (Proc.Imp.Acad., IV, pp.211-214, 1928)
- Relation between Horizontal Deformation and Postseismic Vertical Displacement of Earth Crust which Accompanied the Tango Earthquake (Proc.Imp.Acad., IV, pp.215-217, 1928)
- Postseismic Slow Vertical Displacement of Earth Crust and Isostasy (Proc.Imp.Acad., IV, pp.218-221, 1928)
- Experimental Studies on Form and Structure of Sparks.Part IV (Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res., VIII, pp.197-213, 1928)
- Vertical Displacements of Sea Bed off the Coast of the Tango Earthquake District (Proc.Imp.Acad., IV, pp.296-299, 1928)
- On Gustiness of Winds (Rep. Aeron. Res. Inst., III, pp.235-270, 1928)
- On a Characteristic Mode of Deformation of Sea Bed (Proc.Imp.Acad., IV, pp.364-366, 1928)
- Experiments on the Effect of an Irregular Succession of Impulses upon a Simple Vibrating System (Bull. Earthq. Res. Inst., V, pp.93-110, 1928)
- On the Fluctuation of Sea Level before and after the Great Kwanto Earthquake, 1923-Effect of Cyclones (Bull. Imp. Earthq. Inv. Comm., XI, pp.113-123, 1928)
- Ignition of Gas by Spark and Its Dependency on the Nature of Spark (Proc.Imp.Acad., IV, pp.467-470, 1928)
- On the Effect of Cyclone upon Sea Level (Proc.Imp.Acad., IV, pp.478-480, 1928)
- On the Mechanism of Gliding Spark (Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res., IX, pp.259-264, 1928)
2-4 『寺田寅彦全集 科學編 第四巻』
▼ 『Scientific Papers by Torahiko Terada VOL. 4 1929-1931』、Iwanami Syoten(1936)、pp.363
この第四巻では、多数の写真が添付された正負電極間の火花の研究が目を引きます。砂塊や地殻の変形、関東の地殻変動、火山、対流セル、地震で倒壊した家屋の分布や東京の大火災の物理的検討など。地震に伴う発光現象なども研究しています。
- Experimental Studies on Form and Structure of Sparks.Part V (Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res., X, pp.43-68, 1929)
- Experimental Investigations of the Deformation of Sand Mass by Lateral Pressure (Bull. Earthq. Res. Inst., VI, pp.109-126, 1929)
- A Long Period Fluctuation in Latitude of the Seismic Activity on the Earth (Bull. Earthq. Res. Inst., VI, pp.333-343, 1929)
- Ignition of Combustible Gases with Three-Part Spark (Proc.Imp.Acad., V, pp.125-126, 1929)
- Experimental Investigations of the Deformation of Sand Mass.Part III (Bull. Earthq. Res. Inst., VII, pp.65-93, 1929)
- On the Effects of the Vapours of Halogen Compounds upon the Form and Structure of Long Sparks (Proc.Imp.Acad., V, pp.197-199, 1929)
- Experimental Studies on Form and Structure of Sparks.Part VI (Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res., X, pp.271-290, 1929)
- On the Forms of Volcanos (Proc.Imp.Acad., V, pp.240-242, 1929)
- On the Form of Volcanos (Bull. Earthq. Res. Inst., VII, pp.207-221, 1929)
- Deformation of the Earth Crust in Kwansai Districts and Its Relation to the Orographic Feature (Bull. Earthq. Res. Inst., VII, pp.223-239, 1929)
- Deformation of the Earth Crust and Topographical Features (Proc.Imp.Acad., V, pp.322-325, 1929)
- On the Difference of Behaviours of Different Parts of Three-Part Spark in Igniting Combustible Gas Mixture (Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res., XII, pp.132-148, 1929)
- Further Researches on Periodic Columnar Vortices Produced by Convection (Rep. Aeron. Res. Inst., IV, pp.447-470, 1929)
- On the Nature of Destructive Earthquakes (Bull. Earthq. Res. Inst., VIII, pp.61-73, 1930)
- Crustal Disturbance in Kwanto Districts (Proc.Imp.Acad., VI, pp.49-52, 1930)
- On the Relation between the Divergence of Horizontal Displacements of Trigonometrical Points and the Vertical Displacements of the Earth Crust (Proc.Imp.Acad., VI, pp.53-55, 1930)
- A Physiological Optical Effect Produced when the Image of Long Spark is Projected upon Retina (Abstracts, Bull.Inst.Phys.Chem.Res., IX, p.30, 1930)
- Projection of Long Spark upon the Yellow Spot of the Retina (Nature, CXXV, p.528, 1930)
- Further Studies on Periodic Columnar Vortices Produced by Convection (Proc.Imp.Acad., VI, pp.150-153, 1930)
- Experimental Studies on Form and Structure of Sparks.Part VII (Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res., XIII, pp.207-230, 1930)
- Preliminary Experiments on the Modes of Propagation of Surface Combustion (Abstracts, Bull.Inst.Phys.Chem.Res., IX, pp.53-55, 1930)
- Preliminary Experiments on the Modes of Propagation of Surface Combustion (Proc.Imp.Acad., VI, pp.232-235, 1930)
- On the Heat Generated by the Deformation of the Earth Crust (Bull. Earthq. Res. Inst., VIII, pp.377-382, 1930)
- On Luminous Phenomena Accompanying Earthquakes (Proc.Imp.Acad., VI, pp.401-404, 1930)
- On the Slow Migratory Motion of the Volcanic Activity in Japan (Hitherto unpublished)
- On the Curvature of Islands Arc (Bull. Earthq. Res. Inst., IX, pp.144-150, 1931)
- Experimental Studies on Form and Structure of Sparks.Part VIII (Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res., XV, pp.189-217, 1931)
- On the Curvature of Islands Arc and Its Relation to the Latitude (Proc.Imp.Acad., VII, pp.143-145, 1931)
- On Heterogeneous Distribution of Houses Destroyed by Earthquake (Proc.Imp.Acad., VII, pp.146-149, 1931)
- Analogy of Crack and Electron (Proc.Imp.Acad., VII, pp.215-217, 1931)
- Physical Investigations of Conflagrations in Tokyo (Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res., XVI, pp.69-90, 1931)
- On Luminous Phenomena Accompanying Earthquakes (Bull. Earthq. Res. Inst., IX, pp.225-254, 1931)
- On Cracks and Fissures-Their Physical Natures and Significances (Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res., XVI, pp.159-171, 1931)
- Earthquake and Thunderstorm (Bull. Earthq. Res. Inst., IX, pp.387-397, 1931)
- Relation between Frequencies of Earthquake and Thunderstorm (Proc.Imp.Acad., VII, pp.341-343, 1931)
- Action of Volcanic Ash and Pumice on Oils-A Hint on the Origin of Japanese Tertiary Oil Fields (Proc.Imp.Acad., VII, pp.348-350, 1931)
2-5 『寺田寅彦全集 科學編 第五巻』
▼ 『Scientific Papers by Torahiko Terada VOL. 5 1932-1936』、Iwanami Syoten(1938)、pp.319+27
この第五巻には、日本における石油の起源、群発地震、地震と漁業、土佐湾の地形、津波等など、地球物理学関連が収録されています。有名な「生命と割れ目」や家畜の体色模様の物理的検討、随筆「藤の実」、墨流しに関連した論文があります。また、巻末には、第一巻から第五巻までの総合索引があります。
- Action of Volcanic Ashes on Oils-A Hint on the Origin of Japanese Petroleum (Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res., XVII, pp.265-293, 1932)
- On Swarm Earthquakes (Bull. Earthq. Res. Inst., X, pp.29-34, 1932)
- Cracks Produced on the Surface of Dielectrics by Gliding Spark (Proc.Imp.Acad., VIII, pp.1-4, 1932)
- Deformation of the Rhombic Base Lines at Mitaka and Earthquakes in Kwanto (Proc.Imp.Acad., VIII, pp.8-11, 1932)
- Microscopic Cracks Produced by Electric Spark (Nature, CXXIX, pp.168-169, 1932)
- Earthquakes and Fisheries (Proc.Imp.Acad., VIII, pp.83-86, 1932)
- On Some Probable Influence of Earthquakes upon Fisheries (Bull. Earthq. Res. Inst., X, pp.393-401, 1932)
- Deformation of the Rhombic Base Lines at Mitaka and Earthquake Frequency in Kwanto Districts (Bull. Earthq. Res. Inst., X, pp.402-410, 1932)
- Forest-Fires and Weathers (Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res., XVIII, pp.205-222, 1932)
- Water-Jet Affected by Tobacco Smoke (Nature, CXXIX, pp.614-615, 1932)
- Change of Depth in the Bay of Tosa (Proc. Imp. Acad., VIII, pp.159-162, 1932)
- Change of Depth in the Bay of Tosa (Bull. Earthq. Res. Inst., X, pp.560-568, 1932)
- Tilting and Strength of Earth’s Crust (Proc. Imp. Acad., VIII, pp.288-291, 1932)
- Preliminary Report on Microscopic Crack upon the Surface of Dielectrics Produced by Gliding Spark (Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res., XIX, pp.49-58, 1932)
- Foreword to the Paper“On Hollow Spindle-shaped Liquid Jet” by K. ITo (Rep. Aeron. Res. Inst., VI, p.443, 1932)
- On the Result of Revision of Precise Levelling along the Pacific Coast from Okitu to Kusimoto, 1932 (Proc. Imp. Acad., VIII, pp.410-412, 1932)
- The Result of the Recent Revision of Precise Levelling on the Route from Tokyo to Huzimi via Takasaki and Suwa (Proc. Imp. Acad., VIII, pp.413-416, 1932)
- On the Motion of a Peculiar Type of Body Falling through Air-Camellia Flower (Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res., XX, pp.114-127, 1933)
- Distribution of Terrestrial Magnetic Elements and the Structure of Earth’s Crust in Japan (Proc. Imp. Acad., IX, pp.3-5, 1933)
- Kitakami River Plain and Its Geophysical Significance (Proc. Imp. Acad., IX, pp.6-8, 1933)
- Result of the Precise Levelling along the Pacific Coast from Koti to Kagosima, 1932 (Proc. Imp. Acad., IX, pp.159-162, 1933)
- On a Measure of Uncertainty regarding the Prediction of Earthquake Based on Statistics (Proc. Imp. Acad., IX, pp.255-257, 1933)
- On the Mechanism of Spontaneous Expulsion of Wistaria Seeds (Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res., XXI, pp.233-241, 1933)
- Foreword to the Paper“Thermal Convection of Liquid, Laden with Some Powder”by Y.HUDINO (Rep. Aeron. Res. Inst., VII, pp.419-420, 1933)
- Earthquake and Fisheries.II (Bull. Earthq. Res. Inst., XI, pp.714-716, 1933)
- Luminous Phenomena Accompanying Destructive Sea-Waves(Tunami) (Proc.Imp.Acad., IX, pp.367-369, 1933)
- Luminous Phenomena Accompanying Destructive Sea-Waves(Tunami) (Bull. Earthq. Res. Inst., Suppl., I, pp.25-34, 1934)
- On Physical Properties of Chinese Black Ink.Part I (Proc.Imp.Acad., X, pp.10-12, 1934)
- Experimental Studies on Colloid Nature of Chinese Black Ink.Part I (Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res., XXIII, pp.173-184, 1934)
- On a Regularity in Topographical Features of North-East Japan (Proc.Imp.Acad., X, pp.65-68, 1934)
- On the Modes of Fracture of a Layer of Powder Mass (Proc.Imp.Acad., X, pp.143-146, 1934)
- On the Physical Meaning of Periodic Structure in Earth’s Crust (Proc.Imp.Acad., X, pp.147-150, 1934)
- Revision of Precise Levelling along R.Tenryu, from Simosuwa to Kakegawa, 1934 (Proc.Imp.Acad., X, pp.257-259, 1934)
- On the Stability of Continental Crust (Proc.Imp.Acad., X, pp.260-263, 1934)
- On the Stability of Continental Crust (Bull. Earthq. Res. Inst., XII, pp.451-458, 1934)
- Crack and Life (Abstracts, Bull.Inst.Phys.Chem.Res., VII, pp.45-46, 1934)
- Hot Springs and Deformation of Earth’s Crust (Proc.Imp.Acad., X, pp.410-413, 1934)
- On Bathymetrical Features of the Japan Sea (Bull. Earthq. Res. Inst., XII, pp.650-655, 1934)
- Results of Revision of Precise Levelling in Tohoku Districts (Proc.Imp.Acad., X, pp.557-560, 1934)
- Vertical Movement of Earth’s Crust and Growth of Coral Reef (Proc.Imp.Acad., X, pp.643-645, 1934)
- On Some Optical Illusions (Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res., XXVI, pp.109-121, 1935)
- Hot Springs and Deformation of Earth’s Crust.Part II (Proc.Imp.Acad., XI, pp.99-101, 1935)
- Experimental Studies on Colloid Nature of Chinese Black Ink.Part II (Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res., XXVII, pp.75-92, 1935)
- Cataphoresis of Chinese Ink in Water Containing Deuterium Oxide (Proc.Imp.Acad., XI, pp.214-215, 1935)
- Relation between Topography and Vertical Displacement of Earth’s Crust (Proc.Imp.Acad., XI, pp.222-223, 1935)
- Colloids and Seismology (Bull. Earthq. Res. Inst., XIII, pp.562-567, 1935)
- Geographical Distribution of Hot and Mineral Springs and Deformation of Earth’s Crust (Bull. Earthq. Res. Inst., XIII, pp.576-585, 1935)
- Physical Morphology of Colour Pattern of Some Domestic Animals (Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res., XXVII, pp.263-274, 1935)
- Experiments on Radial Cracks Produced by Percussion upon Glass Plate with Initial Thermal Strain (Honda A (Honda Anniv.Vol.of Sc.Rep.Tohoku Univ., pp.57-61, 1936)
- Crustal Deformation along the Line of Levels from Miyako to Aomori (Proc.Imp.Acad., XII, pp.4-6, 1936)
- Landslide at Hatano (Bull. Earthq. Res. Inst., X, pp.198-199, 1932)
- On Two Cases of Minor Eruption of Mt.Asama (Bull. Earthq. Res. Inst., XIII, p.805, 1935)
Contents of Volumes I-V
Subject Index to Volumes I-V
2-6 『寺田寅彦全集 科學編 第六巻』
▼ 『Scientific Papers by Torahiko Terada VOL.6 1905-1935』、Iwanami Syoten(1938)、pp.327
最終巻では、明治38年から昭和10年に学術雑誌に発表された邦文論文を収録しています。英文論文と同等のタイトルの論文が多数あります。関東大震災における大火を調べた論文には、多数の写真が添付されています。「53 割れ目と生命」は細胞核やそれに伴う細胞分裂を扱ったものですね。なお、巻末には索引がついています。
- 高知縣下の龍卷に就て・ (氣象集誌, 第24年, 251-254頁, 1905)
- 地震の頻度と氣壓の勾配との關係に就て・ (氣象集誌, 第28年, 1-11頁, 1909)
- 綱類腐敗に關する試驗・ (水產講習所試驗報吿, 第9卷, 169-187頁, 1914)
- 各種綱絲類の腐朽に就て・ (水產講習所試驗報吿, 第9卷, 188-208頁, 1914)
- 新島に就て・ (地質學雜誌, 第21卷, 1-7頁, 1914)
- 筑波山の氣溫に就て・ (氣象集誌, 第33年, 467-474頁, 1914)
- 網に對する水の抵抗の硏究(第1次報吿)・ (水產講習所試驗報吿, 第10卷, 1-23頁, 1915)
- 海鳴に就て・ (氣象集誌, 第34年, 1-5頁, 1915)
- 氷の表面に現はれる扇形の模樣・ (氣象集誌, 第38年, 351-354頁, 1919)
- Nippon no Kaigan no zyunino Basyo ni okeru Kaze no nitinitino Henkwa・ (航空硏究所報吿, 第1卷, 33頁, 1922)
- 氣象學上の問題に群(Group)の槪念を應用する事の可能性に就て・ (氣象集誌, 第41年, 452-457頁, 1922)
- 相模灣海底變化の意義並に大地震の原因に關する地球物理學的考察・ (震災豫防調査會報吿, 第100號乙, 63-72頁, 1925)
- 相模灣から起つた津浪の傳播に關する調査報吿・ (震災豫防調査會報吿, 第100號乙, 113-120頁, 1925)
- 大正12年9月1日2日の旋風に就て・ (震災豫防調査會報吿, 第100號戊, 185-227頁, 1925)
- 地震波傳播の異常に就て・ (地理學評論, 第1卷, 841-851頁, 1925)
- Ryutai no Undo ni kwansuru Zikken・ (航空硏究所報吿, 第2卷, 85頁, 1926)
- Ryutai no Undo ni kwansuru Zikken(Mae kara no Tuduki) (航空硏究所報吿, 第2卷, 285-286頁, 1927)
- 彈性波の實驗(第1報)・ (地震硏究所彙報, 第3號, 55頁, 1927)
- 日本海沿岸の島列に就て・ (地震硏究所彙報, 第3號, 67頁, 1927)
- Ryutai no Tairyu ni yotte dekiru syukitekino Udu no Retuni kwansuru Zikken・ (航空硏究所報吿, 第3卷, 1-2頁, 1928)
- 液面に浮ぶ粉狀物質の層の變形に關する實驗並に地球物理學上に於ける類例現象・ (地震硏究所彙報, 第4號, 第21頁, 1928)
- 砂層の崩壞に關する實驗(第1報)・ (地震硏究所彙報, 第4號, 33-56頁, 1928)
- 岸上冬彥, 小平孝雄著“土佐海岸に於ける地殼表面の高低に就て”への追記・ (地震硏究所彙報, 第4號, 64-65頁, 1928)
- 土佐國南海岸の地形に就て・ (地震硏究所彙報, 第4號, 67-73頁, 1928)
- Kaze no Sokudo no hukisokuna Henkwa ni tuite・ (航空硏究所報吿, 第3卷, 233-234頁, 1928)
- 風の息に就て・ (航空硏究所彙報, 第5卷, 197-202頁, 1928)
- 不規則なる衝擊群に因る振動系の運動に關する實驗・ (地震硏究所彙報, 第5號, 93頁, 1928)
- 砂層の崩壞に關する實驗(第2報)・ (地震硏究所彙報, 第6號, 109頁, 1929)
- 地球上に於ける地震活動地域平均緯度の長期移動・ (地震硏究所彙報, 第6號, 333頁, 1929)
- 砂層の崩壞に關する實驗(第3報)・ (地震硏究所彙報, 第7號, 93頁, 1929)
- 火山の形・ (地震硏究所彙報, 第7號, 221頁, 1929)
- 關西地方の地殼變形並に現在地形との關係・ (地震硏究所彙報, 第7號, 239頁, 1929)
- 對流に因る週期的柱狀渦の生成に關する實驗・ (航空硏究所彙報, 第6卷, 715-718頁, 1929)
- 破壞的地震に就て・ (地震硏究所彙報, 第8號, 73頁, 1930)
- Sparkの光像を網膜に投射する際に生ずる生理光學的効果・ (理化學硏究所彙報, 第9輯, 287-289頁, 1930)
- 沿面燃燒に關する豫備的實驗・ (理化學硏究所彙報, 第9輯, 551-560頁, 1930)
- 地形圖に於ける傾斜勾配分布の統計的硏究方法に就て・ (地理學評論, 第6卷, 653-661頁, 1930)
- 地殼の變形に因る熱の發生 (地震硏究所彙報, 第8號, 382-383頁, 1930)
- 嶋弧の曲率に就て (地震硏究所彙報, 第9號, 150頁, 1931)
- 地震に伴ふ發光現象に就て (地震硏究所彙報, 第9號, 254-255頁, 1931)
- 地震と雷雨との關係 (地震硏究所彙報, 第9號, 397頁, 1931)
- 地震群に就て (地震硏究所彙報, 第10號, 35頁, 1932)
- 秦野に於ける山崩 (地震硏究所彙報, 第10號, 192-198頁, 1932)
- 地震と漁獲との關係 (地震硏究所彙報, 第10號, 401頁, 1932)
- 三鷹村菱形基線の變形と關東地方に於ける地震頻度との關係 (地震硏究所彙報, 第10號, 410頁, 1932)
- 土佐灣の海底變化 (地震硏究所彙報, 第10號, 568-569頁, 1932)
- 地震と漁獲(第2報) (地震硏究所彙報, 第11號, 716頁, 1933)
- 霜柱の融解による地面の縞模樣 (科學, 第3卷, 502-503頁, 1933)
- 津浪に伴ふ發光現象 (地震硏究所彙報別册, 第1號, 35頁, 1933)
- 生物と割れ目 (科學, 第4卷, 148-149頁, 1934)
- 麥畑の地面に現はれる弧狀線模樣 (科學, 第4卷, 240頁, 1934)
- 大陸地殼の安定度に就て (地震硏究所彙報, 第12號, 459頁, 1934)
- 割れ目と生命 (理化學硏究所彙報, 第13輯, 817-829頁, 1934)
- 天氣の週期に關する俗說の一例 (科學, 第4卷, 364-265頁, 1934)
- 日本海海底の形態 (地震硏究所彙報, 第12號, 656頁, 1934)
- コロイドと地震學 (地震硏究所彙報, 第13號, 567-568頁, 1935)
- 溫泉及鑛泉の分布と地殼運動 (地震硏究所彙報, 第13號, 586頁, 1935)
- 淺間山小爆發の二例に就て (地震硏究所彙報, 第13號, 801-804頁, 1935)
索引
3.国立国会図書館/個人送信サービスから
このコーナーでは、国立国会図書館/デジタルコレクションの個人送信サービス(無料)を利用して、手元端末で閲覧可能な書籍を紹介します(PC・タブレット推奨)。記事のバナー【国立国会図書館デジタルコレクション】からログイン画面に入ります。未登録の場合、そこから「個人の登録利用者」の本登録(国内限定)に進むことができます。詳細は当webサイトの記事「国立国会図書館の個人向けデジタル化資料送信サービスについて」をご覧下さい。
3-1 小林惟司『寺田寅彦の生涯』、東京図書(1977)
▼ 小林惟司『寺田寅彦の生涯』、東京図書(1977)、pp.322
理系の話しも含めた系統的な評伝ならば、ここで紹介する小林惟司(1930-)『寺田寅彦の生涯』だろうと思います。小林惟司(ただし)は、日本における生命保険研究のパイオニアとのことで、関連する専門書を多数出版していますが、寺田寅彦、二宮尊徳、犬養毅などの評伝などもあります。小林惟司『寺田寅彦の生涯』の初版の帯には
寅彦の生誕100年を飾る初の本格的評伝!!
従来の寅彦像に新しい光をあてた筆生の力作。寅彦の思想は普遍性そのものである。今日の立場からそれを掘り起こすことができた。従来あまり語られなかった人間的側面を照らしだした名篇。
と書かれています。2段組みで、多くの写真があり、まさに「本格的評伝」です。ただ、寺田家に関する記述の中には、「多量の偽りの情報がある」として、寅彦の長男、寺田東一氏が東京新聞紙上で具体例を挙げて抗議していますから、「あまり語られなかった人間的側面」のなかでも、家庭内の話しは鵜呑みにできないようです。小林の『寺田寅彦の生涯』の寺田家を巡る記述に疑問をもつ研究者や編集者のひとりが「還暦」前後だった山田一郎(1919-2010)です。『寺田寅彦覚書』(1981)とその続編『寺田寅彦 妻たちの歳月』(2006)が代表作で、『寺田寅彦覚書』は国立国会図書館/個人送信サービスで閲覧できます。
≫当サイトの関連記事:NDL理系書通信 第3報「寺田寅彦」の関連箇所へ
ところで、本書『寺田寅彦の生涯』には「理化学研究所および寺田物理学」という章があり、その「弟子の養成」という節に、寅彦の弟子の “系譜山脈” がまとめられています。これは、寺田物理学の内容を、地震学、気象学、農業物理学、水産物理学・海洋学、火災物理学、熱力学、膠質物理学、統計物理学、その他に大きく分類したのち、それぞれの分野をさらにいくつかのテーマに分けて、それを担った弟子を列挙しています。これについて、小林は、
当時の日本の大学教授のなかには、自分自身はほとんど実験をしないで、ぜんぶ弟子たちにおこなわせ、できあがった成果だけを自分の名前で発表するという例がめずらしくなかった。 (中略) それにくらべたら寅彦は、はるかに民主的であった。弟子たちが自分でおこなった実験の努力をたかく評価して、研究者としての弟子をどんどん前面に押し出してくれたのである。
と述べています。さらに、驚くべき話しが続くのですが、これ以上の深入りは避けておきましょう。ぜひ、本書を吟味してください。
生涯ゆかりの地
寅彦の系族
寅彦をめぐる女性たち
宗教・芸術・人のこと自分のこと
理化学研究所および寺田物理学
運命と死
付録 寺田家系図/あとがき/索引
(小林惟司 著『寺田寅彦の生涯』,東京図書,1977.6. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12500500)
3-2 大森一彦『寺田寅彦研究文献目録 : 明治37年(1904)-昭和42年(1967)』
寺田寅彦自身の著作ではなく、寺田寅彦を扱った文献の目録がいくつか存在します。ここで、紹介するのは、大森一彦(1937-)という方の労作です。それによれば、「寅彦が処女論文を発表した明治37年から昭和42年3月までに発表ならびに刊行された寅彦を主題とする文献、あるいは寅彦と極めて密接な関連のある文献を調査して再録した」もの、とのことです。単行本17冊、単行本所収169編、雑誌特集5、雑誌・新聞所載294編、月報その他72が集められています。圧巻です。
▼ 大森一彦『寺田寅彦研究文献目録 : 明治37年(1904)-昭和42年(1967)』、東北工業大学紀要第3巻(昭和42年7月)別刷り
4.書斎の本棚/図書館の書棚から
このコーナーでは、本文に登場した本、関連書籍をさらに紹介します。
4-1 ロゲルギスト『精選 物理の散歩道』
ロゲルギストは、ロゴス(理、ことば)とエルゴン(仕事、エネルギー)の合成語、ロゲルギークの派生語です。ロゲルギークは、情報理論寄りのノーバート・ウィーナーのサイバネティクスに、物理学寄りのエネルギー概念を導入した新しい理論体系を意味するものとして考案され、ロゲルギークの構築を目指す研究者集団をロゲルギストと称するとのこと。1950年頃に起源をもつ物理学者の集まりで、「ロゲルギスト」という集団筆名で中央公論社の雑誌『自然』(1946.5-1985.5)に随筆を連載し、その記事は、最初は岩波書店から「物理の散歩道」シリーズとして、後に、その続編が中央公論社から「新物理の散歩道」シリーズとして単行本化されました。構成メンバーは
- 近角総信 (C ちかずみ そうしん; 1922-2016)
- 磯部孝 (I いそべ たかし;1914-2001)
- 近藤正夫 (K こんどう まさお;1911-2006)
- 木下是雄 (K2 きのした これお; 1914-2014)
- 高橋秀俊 (T たかはし ひでとし; 1915−1985)
- 大川章哉 (O おおかわ あきや;1918-1987)
- 今井功 (I2 いまい いさお;1914-2004)
の七名です。寺田物理学の流れを継承していて、日常の物理学/科学です。それぞれが異なる専門的知見をもって語ることから、華やかな印象があります。高橋秀俊はパラメトロンの開発者で、当サイトの常連です。
≫ 【書評記事】第1話 渡辺慧『生命と自由』を読み解く:1-3 「パラメトロンの高橋秀俊」へ
≫ 【書評記事】第7話 北川敏男編『サイバネティックス』を読み解く:2.二人目の登壇者:高橋秀俊
本書、
■ ロゲルギスト『精選 物理の散歩道』、岩波文庫(2023)、pp.352
は岩波書店の『物理の散歩道』(全5巻)から16編を精選して一冊にまとめたもので、各メンバーの特色がよくでています。
はじめに——ロゲルギスト精神(近角聡信)/ロゲルギストのメンバー
つめこむ(木下是雄)
洋服は二着交替に着た方がいいか(木下是雄)
「イトー」「ロジョーホコー」「ハーモニカ」(近藤正夫)
パラドックスの効用(今井功)
呼鈴はなぜ鳴るか(高橋秀俊)
シロウトの日本語文法(今井功)
斜め向きに歩こう(今井功)
数理倫理学序説(木下是雄)
千鳥格子の謎解き(近藤正夫)
青空にあいている孔(近角聰信)
水玉の物理(磯部孝)
蛇行よろめき談義(大川章哉)
ぬれた砂はなぜ黒い(木下是雄)
フィゾー法の影武者(近藤正夫)
続 フィゾー法の影武者(近藤正夫)
要約のすすめ・反要約のすすめ(木下是雄)
編者解説(松浦 壮)/単行本版所収巻/雑誌掲載号一覧
4-2 池内了『寺田寅彦と現代』
■ 池内了『寺田寅彦と現代 : 等身大の科学をもとめて』、みすず書房(2005)、pp.258
池内了(1944-)は科学啓蒙書以外にも、寺田寅彦に関する書籍を数冊著しています。本書は2020年、『ふだん着の寺田寅彦』の15年前に出版された池内了、渾身の一冊です。寺田寅彦を神棚に祀るだけの書物を世に出すことを潔しとしないという池内が、まさに苦しみながら本書を生み出す過程が「あとがき」に残されています。『ふだん着の寺田寅彦』と違い、安全保障政策に関する個人的見解を背景に、リキミ過ぎな箇所も散見されますが、「第2章 寺田寅彦が提唱した新しい科学」などは必見です。
はじめに —— 寺田寅彦との出会い
第一章 「二十世紀の豫言」と現代
第二章 寺田彦が提唱した新しい科学
第三章 技術と戦争を巡って
第四章 科学・科学者・科学教育
第五章 自然災害の科学
第六章 科学と芸術
第七章 貧彦と宇吉郎、そして現代
注
あとがき
『ふだん着の寺田寅彦』については、当サイトに関連記事があります。
≫ 【全集探訪】No.1 「寺田寅彦全集 文學編」: 3-1 池内了『ふだん着の寺田寅彦』